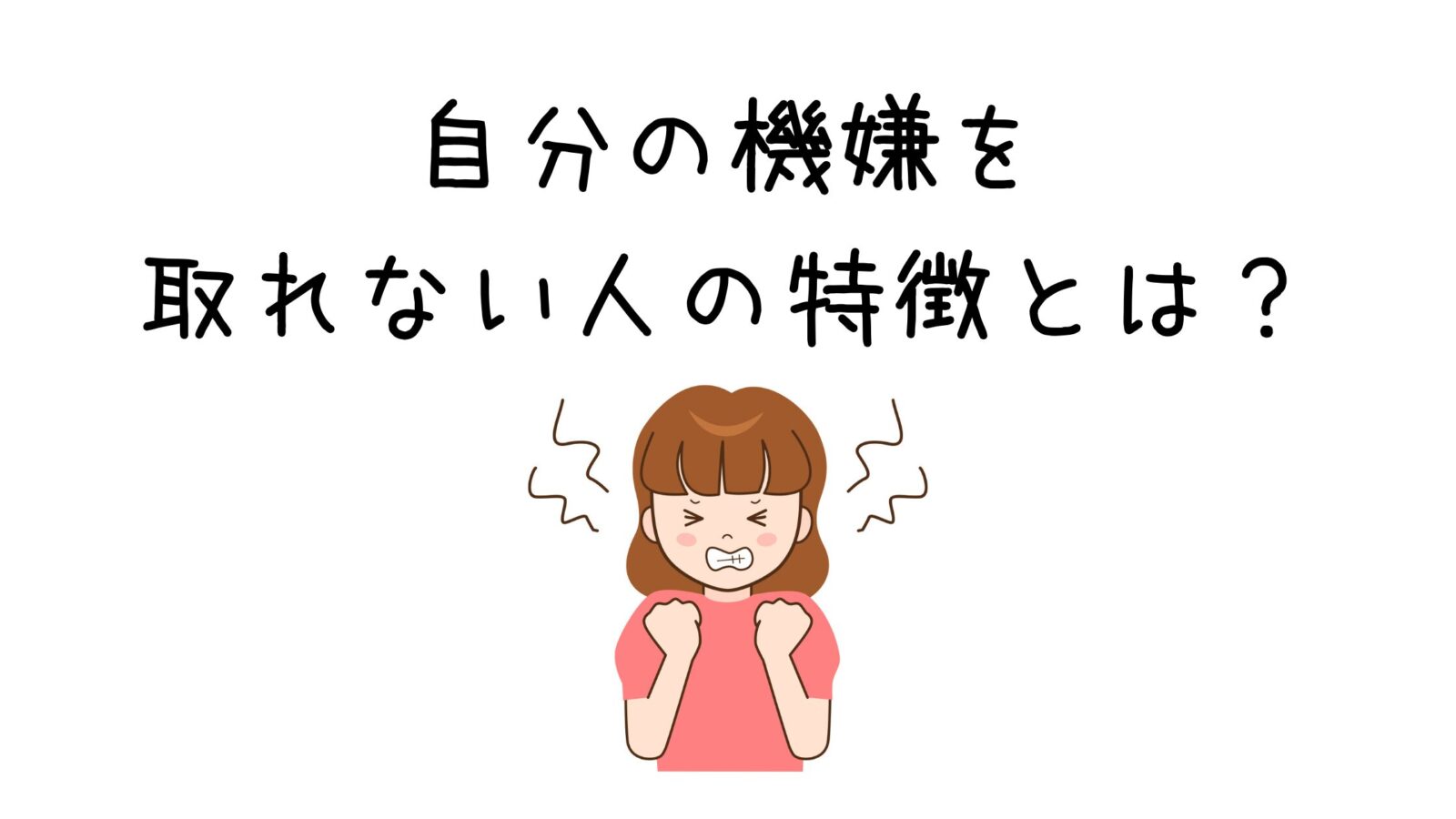職場や家庭で、いつも不機嫌な様子の人に困っていませんか?自分自身が機嫌の波に振り回されて、周囲との関係に支障をきたしていると感じることはないでしょうか。
自分の機嫌をうまくコントロールできない背景には、さまざまな心理的要因が隠れています。コントロールできない要因を理解し、適切な対処法を身につけることで、より良好な人間関係を築くことが可能です。
この記事では、自分の機嫌を取れない人の特徴や原因、効果的な感情コントロール方法、不機嫌な人との付き合い方を紹介します。記事を読むことで、自分や周囲の人の感情をより深く理解し、ストレスの少ない充実した毎日を送りましょう。
自分の機嫌を取れない人の特徴と原因

私たちの周りには、些細なことで機嫌を崩したり、長時間不機嫌な状態が続いたりする人がいます。自分をコントロールできていない行動には、いくつかの共通した特徴や心理的な背景が存在します。
ここでは、自分の機嫌を上手くコントロールできない人の特徴について解説します。
自己肯定感が低い
自分の機嫌をコントロールできない大きな要因の一つは、自己肯定感の低さです。自分に自信が持てず、常に自分を否定的に捉えている人は、些細な出来事でも自尊心が傷つきやすい傾向にあります。
仕事で小さなミスをした際に「自分はダメな人間だ」と必要以上に落ち込んだり、他人からの何気ない一言を重く受け止めすぎたりしてしまいます。自己否定的な考え方は、不機嫌な状態を引き起こし、機嫌の悪い状態を長引かせる原因です。
自己肯定感を高めるには、自分の長所や成功体験に目を向け、小さな成功でも認めていく姿勢が大切です。

できたことやうまくいったことを意識的に探して、認める習慣をつけることで、徐々に自己肯定感を育てていきましょう。
他人からの評価に敏感
人からどう思われているかを過度に気にする傾向も、機嫌の悪さを引き起こす要因の一つです。他人からの評価に敏感な人は、周囲の反応や言動に一喜一憂しやすく、感情の起伏の激しさにつながっています。
特に職場では、上司や同僚からの評価を必要以上に気にすることで、本来なら気にする必要のない些細な言動にも反応してしまい、不機嫌さにつながることがあります。
評価を気にしすぎる状態から抜け出すには、自分の価値は他人の評価だけで決まるものではないという認識を持つことが重要です。完璧を求めすぎず、適度な距離感を保ちながら他者と関わる姿勢を意識的に育てていくことで、より安定した心理状態を保てるようになります。
他責志向の考え方になっている
物事がうまくいかない原因を、常に他人や環境のせいにしてしまう傾向を「他責志向」と呼びます。他責志向になっている人は、自分の機嫌を乱す原因が常に外部にあると考えがちです。
仕事の締め切りに間に合わなかった際に「上司の指示が曖昧だった」「同僚の協力が足りなかった」と考えたり、体調不良の原因を「天候が悪いから」「周りがストレスを与えるから」と解釈したりします。
問題の原因を常に外部に求めることで、自分でコントロールできる部分を見失い、結果として不機嫌な状態が続きやすくなります。
他責志向を改善するには、まず起きた出来事に対して「自分にできることは何か」という視点で考えることが大切です。すべての責任を自分に負う必要はありません。



状況を改善するために自分ができる行動に目を向けることで、より建設的な思考パターンを築けます。
自分の感情を上手に表出できない
感情表現が苦手な人は、ストレスや不満を適切に表現できないことで、不満が蓄積し、結果として不機嫌さとして表れることがあります。特に日本の文化では、感情を抑制することを美徳とする傾向があるため、適切な感情表現ができない問題は珍しくありません。
職場や家庭での人間関係で自分の気持ちをうまく伝えられないことで誤解が生じ、本来は小さな不満が大きなストレスとなって蓄積したりすることがあります。感情を抑え込んだ状態が続くと、些細なきっかけで感情が爆発したり、慢性的な不機嫌さとして表出したりする可能性があります。



感情表現を改善するには、まず自分の感情を正確に認識することから始めましょう。
怒りや悲しみ、不安といった感情に気づき、「私は~と感じています」というような形で表現する練習をすることで、徐々に適切な感情表現ができるようになっていきます。
承認欲求が強い
他者からの承認や認めを強く求める傾向も、不機嫌さの原因です。承認欲求が強い人は、自分の期待通りの評価や反応が得られないと、機嫌を損ねてしまう傾向があります。
日常生活では、SNSでの「いいね」の数に一喜一憂したり、職場での評価に過度にこだわったりする形で現れます。常に他者からの承認を求め、納得できる評価が得られないときに失望や落胆が大きくなります。
健全な承認欲求を保つには、自分の価値は他者からの評価だけでは決まらないことを理解する必要があります。自己承認力を高めることで、外部からの評価に過度に依存しない心理状態を築けます。
ネガティブ思考が強い
物事の否定的な側面に注目しがちな思考パターンは、慢性的な不機嫌さの大きな要因となります。ネガティブ思考が強い人は、良い出来事よりも悪い出来事に意識が向きやすく、感情の不安定さを引き起こしています。
例えば、仕事で9割は成功したプロジェクトでも、1割の未達成部分にばかり目が行ってしまったり、休日の予定で楽しかったことよりも、少しの不都合があった部分を思い出して落ち込んだりしてしまいます。本来なら楽しめるはずの日常生活での喜びも減少させてしまう原因となっています。
ネガティブ思考から抜け出すには、意識的にポジティブな側面に目を向ける習慣をつけることが重要です。
毎日、その日あった良かったことを3つ書き出す習慣をつけたり、失敗や挫折を経験からの学びとして捉え直したりする練習を重ねることで、より柔軟な思考パターンを築けます。
感情をコントロールして自分の機嫌を良くする方法


自分の機嫌をコントロールすることは、簡単ではありません。しかし、適切な方法を知り、実践することで、徐々に感情をマネジメントする力を身につけられます。ここでは、具体的な感情コントロールの方法を解説します。
深呼吸をして一呼吸おく
感情が高ぶったときは、意識的に呼吸を整えることが重要です。深呼吸には、自律神経を整え、心を落ち着かせる効果があることが科学的にも認められています。深呼吸を数回繰り返すことで、興奮した感情を落ち着かせ、冷静な判断力を取り戻せます。



イライラしたときや怒りを感じたときは、すぐに反応せず、まず深呼吸をしましょう。
一呼吸置くことで、後悔するような言動を防ぐことができ、より建設的な対応ができます。
自分の感情を正しく理解して受け入れる
感情をコントロールする第一歩は、まず自分の感情を正確に認識し、受け入れることです。多くの人は不快な感情を抑圧しがちですが、感情を抑えつけることは逆に悪化を招く原因です。
感情を理解するには、「今、自分はどんな感情を感じているか」「なぜそう感じているのか」を具体的に言語化してみることが効果的です。
例えば、「イライラしている」という漠然とした認識を、「締め切りに追われて焦っている」「期待通りの結果が出なくて落胆している」というように、具体的に言語化することで、感情の本質を理解しやすくなります。
自分の感情に気づき否定せずに受け入れることで、適切な対処方法を見つけましょう。
「反応しない練習」は、感情のコントロールが苦手な人にぜひ読んでいただきたい本です。自分の感情に振り回されなくなり、気持ちが穏やかに過ごせるようになります。
紙に書き出して考えをまとめる


頭の中で考えをぐるぐる巡らせているだけでは、ネガティブな感情が増幅されてしまうことがあります。自分の思考や感情を紙に書き出すと、より客観的に状況を把握できます。
「筆記療法」とも呼ばれ、メンタルヘルスの改善に効果があることが研究により示されています。
例えば、不機嫌になった状況、感情、自分の考えを時系列で書き出してみましょう。書き出すことで思考が整理され、問題の本質が見えてきます。
特に、仕事や人間関係で行き詰まりを感じたときは、以下のような項目を書き出すと効果的です。
- 現在の状況
- 自分が感じている感情
- その状況で困っていること
- 考えられる解決策
- 今すぐできる小さな行動
問題を整理すると、漠然とした不安や怒りが具体的な課題として見えてきて、対処しやすくなります。



書き出した内容を見直すことで、自分の感情や思考のパターンにも気づくことも良いでしょう。
人に話を聞いてもらう
悩みや不安を一人で抱え込まず、信頼できる人に話を聞いてもらうことは、感情のコントロールに大きな効果があります。話すことで感情が整理され、新しい視点や解決策が見つかることもあります。
ただし、話を聞いてもらう相手は慎重に選ぶ必要があります。プライバシーを守ってくれる人、適切なアドバイスができる人、あるいは単に話を聞いてくれるだけの人など、状況に応じて相談相手を選びましょう。
専門家に相談することも有効な選択肢の一つです。カウンセラーやメンタルヘルスの専門家は、客観的な立場から適切なアドバイスを提供してくれます。



自分一人では解決が難しいと感じたときは、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。
原因自分論を正しく身につける
自分の機嫌や感情をコントロールする上で重要なのが、「原因自分論」という考え方です。起こった出来事の原因を外部に求めるのではなく、自分にできることは何かを考える姿勢のことです。
しかし、原因自分論は全ての責任を自分に負うということではありません。例えば、仕事でトラブルが発生した場合、「すべて自分が悪い」と自分を責めるのではなく、「この状況で自分にできることは何か」という建設的な視点で考えることが大切です。
下記の動画では、原因自分論についてわかりやすくまとめられています。
原因自分論を身につけることで、不機嫌になった際も、状況を改善するために自分ができる行動に焦点を当てられるようになります。より積極的で前向きな問題解決が可能になり、感情のコントロールもできるようになる考え方です。
リラックス方法を見つけて実践する
ストレス社会と言われる現代において、自分なりのリラックス方法を持つことは、感情コントロールの重要な要素です。自分に合った、効果的なリラックス方法を見つけましょう。
リラックス方法は人それぞれ異なりますが、以下のような方法が一般的に効果があるとされています。
- 軽いストレッチや瞑想
- 音楽を聴く
- アロマテラピー
- 入浴
- 趣味の時間を持つ
上記の方法は、ストレス解消だけでなく、自律神経のバランスを整え、心身をリフレッシュする効果があります。特に、仕事や人間関係でストレスを感じやすい方は、日常生活の中に定期的なリラックスタイムを設けることがおすすめです。
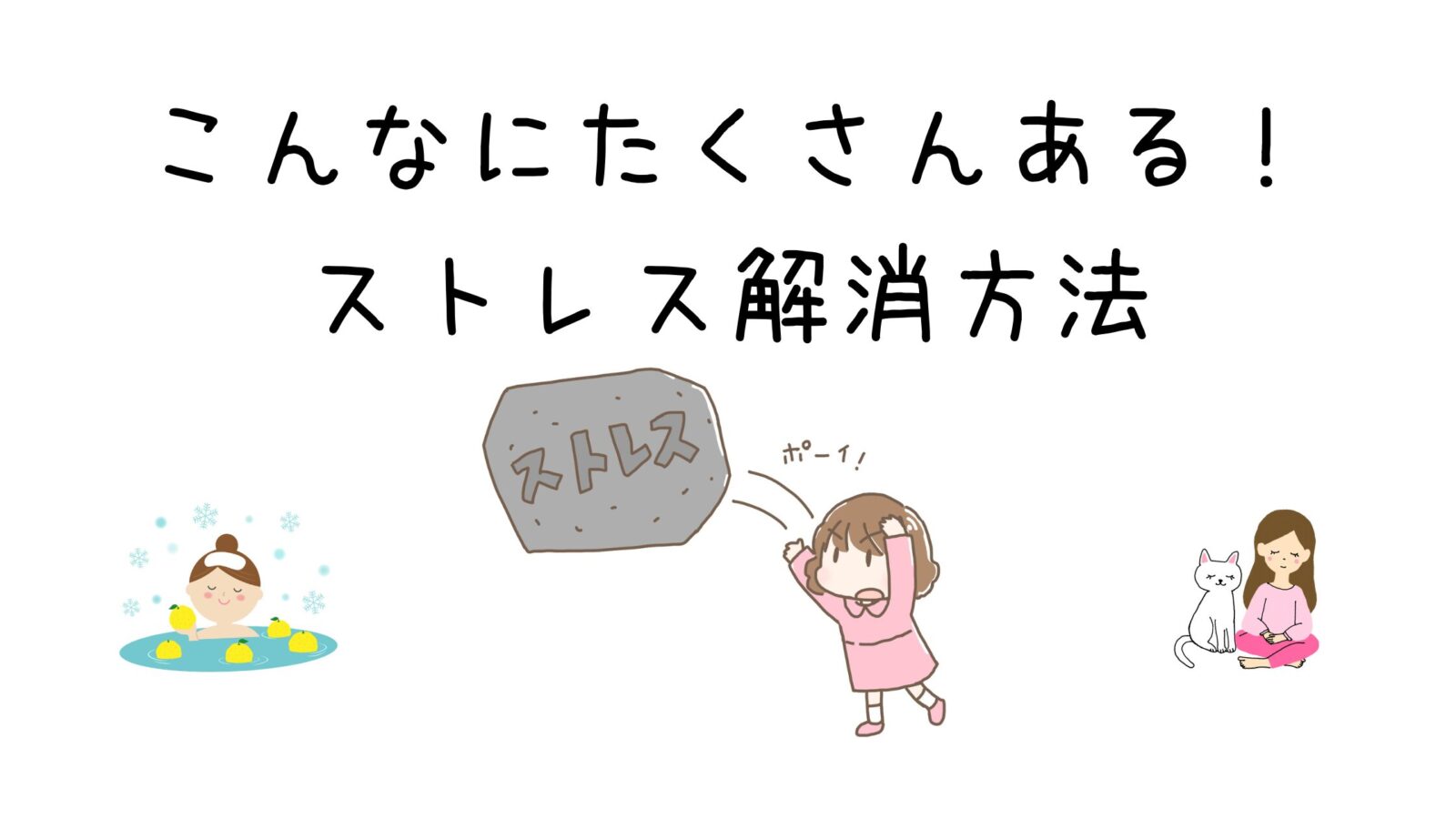
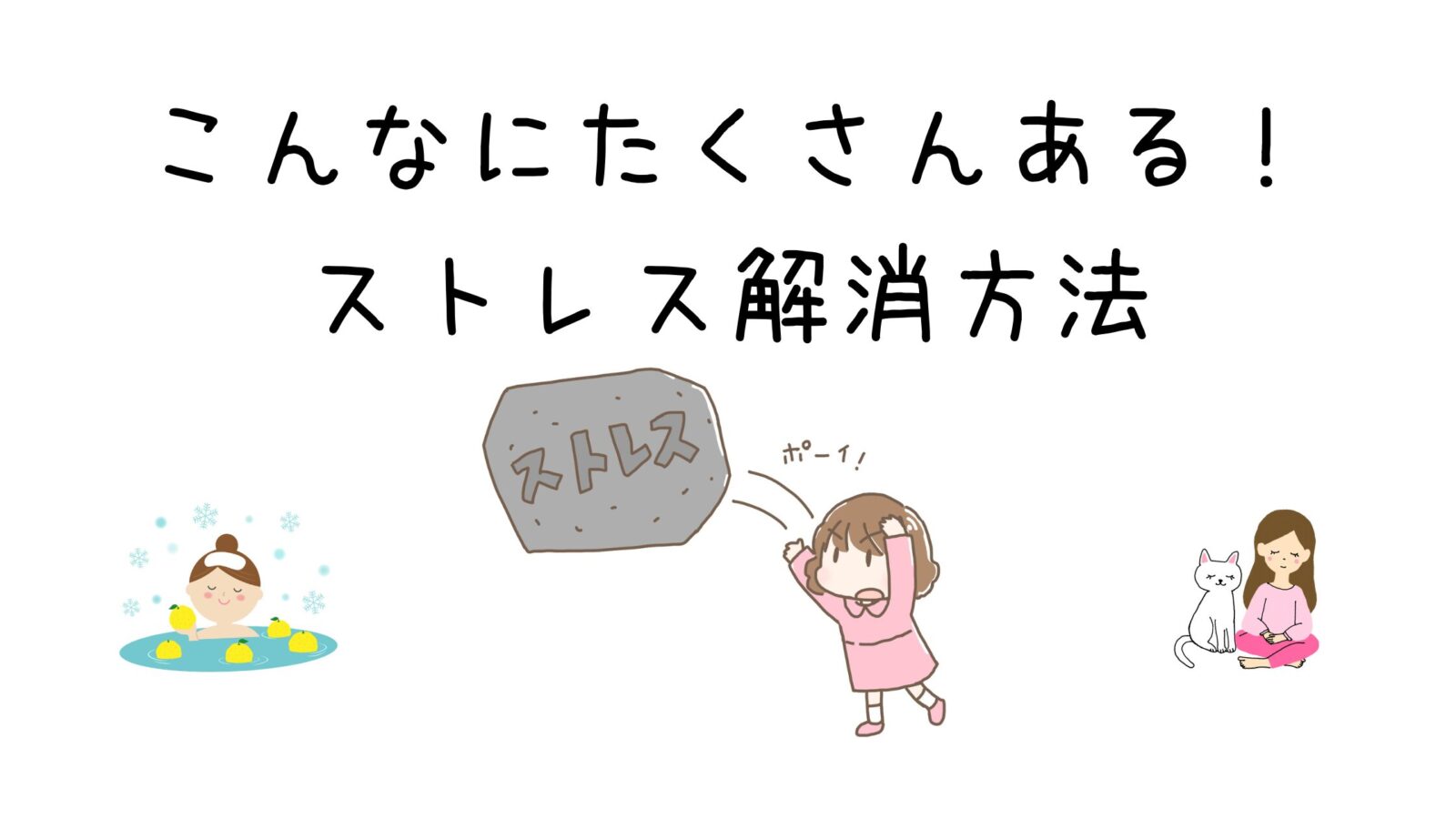
美味しいものを食べる


食事には気分を改善する効果があることが科学的に証明されています。特に、好きな食べ物を味わうことは、脳内の幸福感を司る神経伝達物質であるセロトニンの分泌を促進します。
感情的な食べ過ぎには注意が必要です。不機嫌な時に過度の糖分や脂質を摂取すると、一時的な気分の改善は得られても、その後の体調不良や罪悪感につながる可能性があります。
バランスの取れた食事を心がけながら、好きなものを適度に楽しむという姿勢が大切です。例えば、週末のご褒美としてお気に入りのデザートを食べたり、友人と美味しい食事を共にしたりすることで、心身ともにリフレッシュすることができます。
運動をする


運動は、感情コントロールに効果的な方法の一つです。適度な運動は、ストレス解消ホルモンであるエンドルフィンの分泌を促進し、気分を前向きにする効果があります。特に以下のような運動が効果的です。
- ウォーキングやジョギング
- ヨガやストレッチ
- 水泳
- 筋力トレーニング
- チームスポーツ
運動は、強度や時間を自分に合わせて調整することが重要です。無理なく続けられる運動を見つけ、定期的に実践することで、心身の健康維持につながります。運動を通じて新しい目標を設定し、達成感を味わうことも、感情コントロールに良いでしょう。
\自分に合ったジムが見つかる!ジムのサブスクで気軽に体験/
不機嫌な人に振り回されない!自分の機嫌を取れない人の対処法


周囲に自分の機嫌をコントロールできない人がいる場合、対応に悩むことも多いでしょう。ここでは、不機嫌な人との関係を上手く保ちながら、自分自身のメンタルも守る方法を解説します。
無理に関わらずにそっとしておく
不機嫌な人に対して、すぐに関わろうとするのは逆効果な場合があります。感情的になっている時は、冷静な判断や対話が難しい状態にあることを理解し、適切な距離を保つことが重要です。
感情が落ち着くまで、必要最低限のコミュニケーションに留めることがおすすめです。無理に励ましたり、アドバイスをしたりすることで、かえって状況が悪化する可能性があります。



完全に無視するのではなく、必要な業務連絡は行いながら、相手の状態が改善するのを待つという姿勢が大切です。
相手も自分のペースで感情を整理する時間を得ることができます。
対応に困るときは周囲に相談をする
一人で抱え込まず、上司や同僚、専門家など、信頼できる人に相談することも重要な対処法です。他者の視点を取り入れることで、新しい対応方法が見つかることもあります。
相談する際は、以下のポイントを意識すると効果的です。
- 具体的な状況を説明する
- 自分がどのように感じているかを伝える
- これまでに試みた対応方法を共有する
- アドバイスを求める具体的な内容を明確にする
周囲に相談することで、自分一人で悩みを抱え込まないようにし、より客観的な視点で状況を捉えられます。同じような経験をした人からの具体的なアドバイスを得られる可能性もあります。
話を聞いて一緒に解決策を探す
相手の状態が落ち着いているときは、コミュニケーションを取る良い機会です。批判や否定をせず、まずは相手の話に耳を傾けることが大切です。
傾聴の際は、以下のような姿勢を心がけましょう。
- 相手の話を遮らない
- 共感的な態度で接する
- 解決を急がない
- 非言語コミュニケーション(うなずきや相槌)を意識する
相手が自分の気持ちを話し終えた後で、一緒に解決策を考えていく姿勢を示すことで、より建設的な関係を築くことができます。ただし、すぐに答えを出す必要はありません。時間をかけて、互いに納得できる方向性を見つけていきましょう。
自分が辛い場合は距離を取る
不機嫌な人への対応に疲れを感じたら、適切な距離を取ることも必要です。自分の心身の健康を守ることは、良好な人間関係を維持する上で重要な要素です。



可能な範囲で接触頻度を減らしたり、必要最低限のコミュニケーションに留めたりするなど、自分を守るための境界線を設定しましょう。
特に職場では、業務上必要な関わり以外は控えめにするなど、適切な距離感を保つことを心がけます。決して逃げることではなく、より良い関係性を築くために必要な自己防衛策だと理解することが重要です。
自分の機嫌を取れない人に関するよくある質問


自分の機嫌を取れない人に関する質問をまとめました。自分の感情を上手にコントロールして、機嫌よく過ごす参考にしてください。
自分の機嫌取るのが上手い人とは?
自分の機嫌をうまくコントロールできる人には、いくつかの共通した特徴があります。自己肯定感が高く、感情をうまく表現でき、ストレス対処法を持っているということです。以下のような行動特性を持っています。
- 感情の起伏を認識し、適切に対処できる
- 自分に合ったストレス解消法を持っている
- 他者との適切な距離感を保てる
- 必要に応じて助けを求められる
- 自己肯定感が適度に高い
一朝一夕に身につくものではありませんが、意識的な努力と実践を重ねることで、徐々に習得できます。自分の感情パターンを理解し、適切な対処法を見つけていくことが、感情コントロールの第一歩です。
人をイライラさせてしまう原因は?
人をイライラさせてしまう原因は多岐にわたりますが、主に以下のような要因が考えられます。
- コミュニケーションの不足や齟齬
- 期待と現実のギャップ
- 相手への配慮不足
- ストレス環境の継続
- 互いの価値観の違い
上記の問題を改善するには、まず自分の言動が他者にどのような影響を与えているかを意識することが重要です。相手の立場に立って考え、必要に応じてコミュニケーション方法を調整することで、より良好な関係を築くことができます。
まとめ


自分の機嫌をコントロールすることは、より良好な人間関係を築き、充実した日常生活を送るための重要なスキルです。本記事では、機嫌をコントロールできない人の特徴や、改善方法について解説しました。
自己肯定感の低さや他責志向な考え方、感情表現の苦手さなど、不機嫌の背景には様々な要因があります。改善には、深呼吸や運動といった実践的な方法から、専門家への相談まで、状況に応じた適切なアプローチが有効です。
周囲に不機嫌な人がいる場合は、適切な距離感を保ちながら、状況に応じたコミュニケーションを心がけることが大切です。決して感情を抑え込むのではなく、自分の感情を理解し、適切に表現しながら、より良い人間関係を築いていくことが重要です。